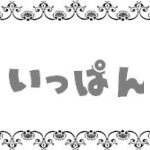トントン拍子で出世する人と、課長止まりの人の「決定的な違い」
石倉秀明:山田進太郎D&I財団COO
マネジメント「40代で戦力外」にならない!新・仕事の鉄則
2025.4.16 6:30 会員限定
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
出世するほどに社内でのポジションの数は減っていく。会社から評価され、順調に出世していく人が共通して持っている能力とは何だろうか。(山田進太郎D&I財団 COO 石倉秀明)
評価される管理職と評価されない管理職の違いとは?
皆さんの中には、いわゆる管理職として働いている人も少なくないだろう。
管理職は責任が重く、仕事もハードであり大変な側面が大きい一方で、自分の裁量で大事な取引などを決められたりと、やりがいも大きいポジションであるのは間違いない。
しかし、プレーヤーでいた時のように自分の成果がはっきりしないこともあり、会社からどう評価されているのかが気になる人も多いのではないだろうか。
筆者はここ10年ほど会社経営の立場(現在は財団の常任理事であり、株式会社における取締役と同じ責務を担っている)にあり、管理職の登用や抜擢などを含め、管理職を評価してきた。その経験から、今回は会社から評価される管理職とそうでない管理職にある能力の違いについて書いていきたい。
企業が管理職に求めるものはたくさん存在する。もちろん任せている部署に課しているミッションや目標の達成は最重要だし、チームマネジメントが円滑であることも大事だ。
一方で、係長、課長、部長、本部長、執行役員などと役職が上がるにつれ、会社内でのポジションの数は減っていく。つまり、課長全員を部長に上げることはできず、選抜をしていくことになる。その選抜に残れるかそうでないかで、管理職としてどこまで昇進できるかは変わってくる。
筆者も数百人の管理職を見てきたが、その中で順調に昇進していく管理職には共通して優れている能力があった。
「部下に適切な仕事をアサインする」ために重要な3つのポイント
それは、部下を適切な仕事にアサインする能力である。
当たり前に感じるかもしれないが、これを実現するのは非常に難しく、複数の能力が高い水準で必要になる。
まず、部下のスキルや能力を正確に見極められることが重要だ。
例えば、目標ややり方が決まっており、一人でタスクを進める仕事であれば、どんどん仕事を進めて目標を達成できる部下がいるとする。しかし、この部下は事業や部署の戦略に合わせて一から自分で施策や企画を考える場面になると、途端にパフォーマンスが上がらない。
そのような部下がいた場合、いくらその部下がチーム内で経験豊富だとしても、企画立案などが重要な仕事にアサインしたらおそらく成果は出ない。それが続けばその部下の評価も下がってしまうだろうし、周囲からも期待されにくくなってしまうかもしれない。
つまり、上司が部下の能力適性を見誤ることは、その部下の今後のキャリアに大きな影響を与えてしまいかねないということだ。
次に、任せる仕事の特徴やその仕事で成果を出すために必要な能力などを把握していなければならない。部下の能力を把握できたとしても、それに適した仕事がどれかを理解し、マッチングできなければ、結局は部下は能力を発揮できない。
そして最後に、部下にとって心地良い難易度を把握する必要がある。
例えば、部下のAさんは自分のできることを増やしたいが、いきなり仕事の難度が大きく上がるとストレスに感じてしまうかもしれない。
そういうタイプの部下には今までよりも少しだけ難度が高い仕事を任せたり、今まではフィードバックしていた仕事を自分で決めてもらったりするなど、少しだけ背伸びをしたアサインメントをすることが必要になる。
仕事の成果は「能力×場所」で決まる
このように3つのポイントをしっかりと把握した上で、部下を適切な仕事にアサインすることが求められるのだ。
経済学や経営学の研究でも、上司が部下のキャリアに与える影響については以前よりかなり多くの研究がされてきている。共通して言われているのは、会社から高く評価されている優秀な上司がいる部下は昇進確率も高くなり、生涯の収入も数%~10%程度高くなるということだ。
これにはいくつかの要因があるとされているが、その中でも最も重要な示唆は、優秀な上司は部下の能力や適性を見極め、その部下が最もパフォーマンスを発揮できる仕事にアサインする能力が高いということ。そしてそれが、ゆくゆくは部下のキャリアに良い影響を与えていると指摘されていることだ。
今まで多くの日本企業では、マネジメントは「イコール管理」だと認識されてきた。部下が言われたことをしっかりやっているかを監視し、できていなければコミュニケーションを取ったり、時には叱咤激励などをしたりしながら、決められたことを決められた通りにやらせる、いわゆる「行動のマネジメント」が中心だった。
しかし、結果を出し続け、会社から高く評価され続けるのは、部下の能力と、その部下が最も力を発揮できる仕事をうまくマッチングさせることで、成果を最大化する能力が高い上司なのである。
これは拙著『CAREER FIT』にも書いたのだが、仕事の成果というのは、能力とそれを発揮する場所の掛け算で決まる。この掛け算は、転職の場面だけではなく、もちろん社内や部署、チーム内で仕事を誰に割り振るかという場面でも同じく重要な要素なのだ。
もし、あなたが管理職として働いていて、チームや部署でうまく成果が出ない部下がいたら、まずはその部下の能力や適性は何かをじっくりと観察し、その能力や特性が最も生かせる仕事にアサインし直すところから始めてみてはいかがだろうか。
『結果を出す人の仕事術』 Kindle、楽天Koboなどで配信中!
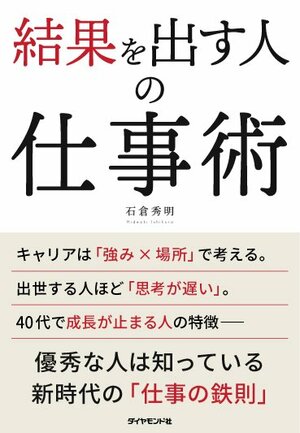
終身雇用の崩壊やリモートワークの普及、生成AIの活用促進で働き方が激変する時代。
求められるのは、いつでも・どこでも・誰とでも「結果を出す」思考法&技術です。
会員限定の連載『「40代で戦力外」にならない!新・仕事の鉄則』の人気記事を再編集して電子書籍化!
新入社員からベテラン社員まで、ビジネスパーソンが活躍し続けるためのヒントが満載の一冊です。
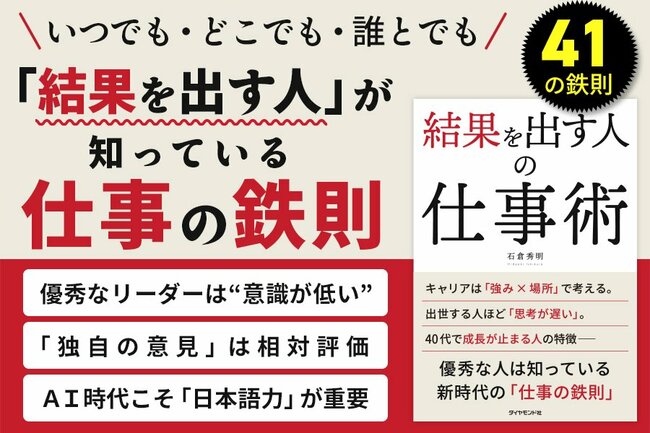
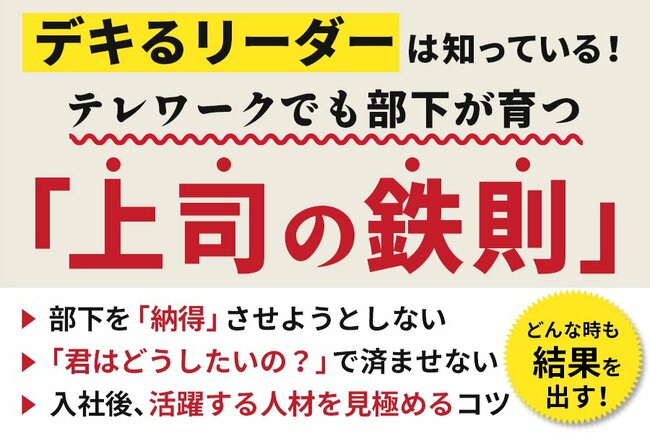
【主要目次】
はじめに
第1章:AI時代に戦力外にならない!「仕事の鉄則」
・仕事で必ず成果を出す人は「三つの能力」を持っている
・説得力がない人の「残念な特徴」
・「独自の意見」を出すたった一つのコツ
・テクノロジーの進化に負けない「準備力」
・40代以上に必要な「真のリスキリング」
第2章:リモートでも部下が育つ!「上司の鉄則」
・新人を成長させようとしてはいけない
・うまくいかないチームが「答えられない」質問
・ダメ上司は「私が責任を取る」で片付ける
・入社後、確実に活躍してくれる人材を見極める方法
・「仕事をしない部下」への対処法
・副業・フリーランス人材を大活躍させる「三つのコツ」
・部下の成長を妨げる「優しい上司」のNG行動
第3章:最小の努力で年収が上がる!「キャリアの鉄則」
・キャリアは「強み×場所」で考える
・年収を上げるために「スキルアップ」よりも大事なこと
・「配属ガチャ」に外れたらどうする?
・AI時代に出世できる人の必須条件