注意すべき表記方法
日本語の文章中では、句点 [。]、読点 [、]を用いることを推奨します。
- 英単語または英文をピリオド、クエスチョンマーク、コンマ、セミコロン、
コロンの後には半角スペースをいれる。前にはいれない。 - 数字、アルファベット、ギリシャ文字、% は半角文字を使う。
- 数字と日本語の間、英単語と日本語の間、数字と単位の間、に半角スペース
をいれる - 数学記号の前後にはスペースをいれない(+, -, x, /)。
例:正(5 ml の)(pH 7.5)、誤(5mlの)(pH7.5)
例外、%、℃ の前にはスペースを入れない。
正(10%、10℃)、誤(10 %、10 ℃)
正(10xTE)、誤(10x TE、10 x TE、10 xTE) - ハイフン、スラッシュの前後にはスペースを入れない。
Rad51-promoting reaction
both Rad51- and Rad52-promoting(and の前とハイフンの間には半角スペ
ース)
phenol/chloroform - 省略記号としてのピリオドとスペースの関係に注意。
Naoto Arai→省略 N. Arai(名字が先の時、Arai, N.):誤(N.Arai)(Arai. N.)
Wolf-Dietrich Heyer→省略 W.-D. Heyer(名字が先の時、Heyer, W.-D.):
誤(W. -D. Heyer)
Arai, N., Nakagawa, T., Nakamura, S. and Inoue, T.
誤(Arai,N., Nakagawa, T, Nakamura. S.and Inoue, T.) - 半角の括弧の前と後ろに半角スペース(但し、句読点の前にはいれない)
例: polymerase chain reaction (PCR) を用いた。
例: 誤 polymerase chain reaction ( PCR)を用いた。
例: polymerase chain reaction (PCR)。誤 polymerase chain reaction (PCR) 。 - ギリシャ文字は、Symbol フォントを使うと半角文字で記述できる。
(Macでマイクロμはoption+mでもよい)
(H2O(下付き小さい)をH2O へ:2を選択して [Ctrl+H]キー)
l 薬品は物質名で記述、分子式では書かない。併記は可能。
例:塩化ナトリウム、塩化ナトリウム(NaCl)
例:リン酸カリウム緩衝液 (pH7.4)、(誤:KPO4 (pH7.4))
例:リン酸二水素カリウム(KH2PO4)、(誤:KH2PO4のみ)
l 論文中に章や項目の番号のみを記載するのは良くない。
誤:Rad buffer (2-2-1) を使用した。←番号のみ、何の数字なのかわからない。
次のように記述する。
例1:Rad buffer は、「2-2-1. 試薬の調製」で記したものを使用した。
例2:Rad buffer (項目2-2-1. 試薬の調製を参照) を使用した。
例3:Rad buffer (項目2-2-1を参照) を使用した。
例4: 2 μlのrad57/NdeI-DNA断片(インサートDNA、項目2-3-1参照)、
1 μlのpET-3a/NdeI(ベクターDNA、項目2-2-3参照)と1 μlの
10xLigation buffer (タカラバイオ)を加え、滅菌超純水で10 μlとした。
l 遠心分離の条件の表示について
同じ回転数でも遠心機のメーカー、機種、ローターによって回転加速度(G)
すなわち、遠心する力が異なります。ですから以下のようなどちらかの表記
が必要です。
遠心機のメーカー、機種、ローター、回転数、時間、温度
例:冷却遠心機、TOMY RS-20BH、BH-4 ローター、12,000 rpm、
20分、4℃
回転加速度G(xg)、時間、温度
例:遠心分離、14,000xg、20分、4℃
l 不適切な表現
不適切:大腸菌が生えた→ 推奨表現:大腸菌が生育した。増殖した。
変なカタカナ:クルード
→ 推奨表現:粗画分の、粗分画の、粗精製の、未精製の、など
共洗い→推奨:操作を書きましょう。(少量のBuffer Aで洗浄し・・)
l 研究室通常使っている表現を論文で書く時
crude extract (粗抽出液)
fractionate(分画する)
fraction(画分)
以下は、旧核酸科学研究室において研究室のマニュアルから抜粋したものである。卒業論文執
筆に際して、参考にすると良い。
7.2.3 実験報告論文の執筆
- 実験報告論文の主要部分は「緒言9」、「材料と方法」、「結果」、「考察」の 4 つ
の章である。これらは互 いに密接に関係しあっているが、執筆に際しては、それぞれ
の章の目的を常に意識していなくてはなら ない。初学者の論文には、往々にして「方
法」と「結果」が未分化であったり、「結果」に記載してい ないことを「考察」にお
いて縷々議論したりする弊が見られる。 - 「緒言」には報告しようとする実験にどのような意義があるのか、過去には当該分
野でどのような報告 がなされているのか、それらの報告をどのように評価して、今回
の実験を計画するに至ったのか等に関 して、文献を引用しながら記述する。ここに引
用される文献は、執筆を開始するまでの数ヶ月の間に、 抄読セミナーで紹介したもの
であるかも知れないし、また、各自で自主学習したものであるかもしれな い。いづれ
にしても、自己の論文の「緒言」で引用しなくてはならない文献は、実験テーマの決定
後の なるべく早い段階で、熟読玩味して、その内容を完全に理解しておく必要がある。 - 緒言においては、報告しようとする内容とあまりにかけ離れたことを記述するのは
見苦しい。たとえば、 DNA を基質とする酵素の性質を記述する際に、Watson と Crick
の Nature の論文を引用する必要は ない。また論文は、随筆や小説ではないので、感
覚的ないしは非科学的な表現は避けるべきである。 - 「材料と方法」は論文を構成する 4 つの章のうちでは執筆しやすい部分である。科
学実験において最も 重要なのは「再現性」であるが、実験報告の再現性は、この章が
如何に正確に記述されているかに依存 している。基本的態度としては、当該部分にし
たがって実験を行えば、執筆者と全く同じ結果を得るこ とが出来るように記述すれば
よい。しかし、読者の知識レベルは様々なので、どの程度まで細かく記述 するべきか
は、一概には決められない。執筆にあたっては過去の卒論を批判的に読んで学習するこ
と。 - 本来は「結果」の項に記述するべきことを、「方法」に混入してしまう例がしばし
ばある。「方法」で は、あくまで個々の実験方法 (定量法、分析法、調製法など)の一
般的やり方を記さなくてはならない。 たとえば、アルカリ溶菌法でプラスミド DNA
を調製して、ある濃度の DNA 試料が得られた場合に は、アルカリ溶菌法の詳細と、
DNA 濃度の測定方法は「方法」の項に記し、得られた DNA の濃度は「結果」の項に
記すべきである。 - また「材料と方法」の章のほとんどを箇条書で済ませてしまう論文も散見されるが、
これは好ましくない。箇条書に出来る部分であっても、主語・述語のある正規の文章で
記述すること。 - 「結果」は実験報告論文の最も重要な部分であり、卒業実験の成果はここに集約
される。しかし、学部 4 年次の 1 年間 (実質は半年間以下) では、科学の世界に新し
い知識をもたらすような新発見をなしう ることはまれであり、時としては何の成果も
得られないだけではなく、基礎的な技術の修得ができないために、いわゆる「失敗」の
くり返しで終ってしまう場合もある。 - しかし、もし不幸にしてそのような結果しか得られなかったとしても、そこにい
たった過程を正しく記述し、何故に失敗したのか、どのよう工夫すればその失敗を避け
ることができたと判断するか、など を正確に解りやすく記述することが出来れば、卒
業論文としての評価は決して低いものとはならない。 逆に、かなり興味深い実験結果
を得ることができても、その実験の再現性を保証する正しい記述が出来 ていなければ、
論文としての評価は極めて低い。 - 「結果」は単なる記録の羅列ではない。1 年間に行った数十回の実験結果を取捨選
択し、その意味する ところをもっとも効果的に読者に伝える必要がある。しかし、成
功したがごとく見える結果のみを恣意 的に抜出すのはもちろん許されない。たとえば
10 回同じことを試みて、そのうち 1 回の実験で期待 していた結果を得たとしても、
おそらくその実験には再現性がないであろう。卒業実験報告におけるこ の場合の正し
い判断は、期待通りの実験結果のみを記述するのではなく、10 回のうち 9 回は期待に
背 く結果が得られたという事実を記し、9 回も期待通りにならなかったのはなぜなの
か、さらに、たった 1 回が期待通りになったのはなぜなのかを議論することである。 - 「考察」においては「緒言」で提示した実験目的を「結果」においてどのように達
成できたか、ある いは出来なかったかを記す。多くの場合は、目的が 100% 完全に満
たされることはないであろうから、 不完全な部分はなぜ生じたのか、完全ならしめる
ためには今後どのようなことを実験すればいいのか、 なども記述する必要があろう。
どのような議論をするにしても、その内容は「緒言」と「結果」に関連 する事項にと
どめるべきであり、徒に大風呂敷を広げ、空論を重ねるのは極めて見苦しい。
The Life in the Laboratory of Nucleic Acid Science LNAS1999より抜粋(Lifroot.pdf)

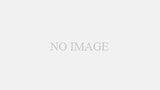
コメント